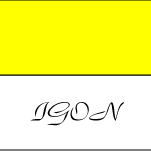生前契約=葬儀のみ ではありません
そこにはもちろん遺言が必要です
そこには、もちろん弁護士や司法書士などが必要です
自分だけが自分の死を知らされてなく、最期を迎えることこそ惨めだと思いませんか?
最期こそやりたかったことを成し遂げるのも人生です
家族、そして親子とは?
遺言は亡くなってからの執行です。
生前契約があれば生きている間にどうしたいかも考えることができるでしょう。
諦めないで欲しいです。
家族のあり方とは
家族法があり、民法(明治29年法律第89号)によって定められており、親族法と相続法のを合わせた上位概念である、身分法とのこと。
2018年の相続法大改正に加え,成年年齢・特別養子・子の引渡し等に関する法改正されているが概ね明治29年(1896年)から変わっていない。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/CC1_2.pdf
第一条
1 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
この明治民法の「家」制度が日本の家族に及ぼした影響を考える必要があります
そして「親子」は日本固有の概念であることも
- 親と子、Parents and Children、Father & Mother
- 兄弟、姉妹 → brothers, sisters, Elder/Sibling
- 中国でも存在しない(中国は自分中心で考える)
- 「父母与子女」になる
しかし、民法上「家族」という定義がないんです
民法では家族の範囲を正確に定めていないという事です
ただし、民法では「親族」については定義をして、親族法というのがあります。
2018年見直しがありちょうど一年前の2019年1月13日に施行(ゆいごん.みんなにても相続権が変更したので説明しました)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
更に2019年7月1日施行された居住権とについても
詳しく画像にてこちらに表示されています
http://www.moj.go.jp/content/001310392.pdf
家族について明確な定義がないが、人が亡くなったときはどうなるのか?
相続において、死者は人権がない。
実は例として、霊柩車が二人乗りだが、ご遺体を含めると3名になる。
トラック(運搬)ということなので、本来は喪主も乗車してはならないのだが、慣例として営業車であり、本来なら生きた人も乗せているので、二種免許保有せねばならないが、普通免許での運転を認めている
次に人権がなければ生前予約が成り立たないわけです
死後事務委任契約を遂行するには「人権」が亡くなった人にもなければ遂行できないわけでです。
生前契約があることによって、死後どうしたいか伝えることができます。
例えば末期がんにおかされた方が、自分の余命を伝えられてなく、ただ元気になるだろうという気持ちで病床で亡くなった場合、知っていた人たちはどう責任を取るんだ?
生前契約と遺言があって、それを告知義務があったら、命があったときに、もっと素晴らしい人生の楽しみ方ができたのではと思うばかりです。
更に離婚→再婚で増える複合家族の場合も生前契約できちんと定義しておく必要があるでしょう。
あとは費用の課題です
どうやって補うか
生命保険会社も破綻し吸収される時代
吸収されたらその保保険は生きているのか